Nikeへの就職をきっかけにスニーカー業界で働くことになった高見さんでしたが、実際にその中に入ると、実際の景色は想像とは全く異なるものでした。
インターネットもなく事前に事業の内容について調べられる方法もなかったため、入社してから「なにがしたいの?」という問いかけに対しても、何があるのか、何が出来るのか、右も左もわからない状態だったといいます。
事務作業か外回りかの2択になり、外回りを希望した高見さんは営業部に配属に。
一般職と事務職に分けられるなかで、営業として働く高見さんも事務職という扱いでした。
入社当時の日本では「女性社員はお茶汲み、コピー取りをするもの」という風潮があり、外回りの仕事もしつつ、お茶汲みやコピー取りをこなし、席に戻ると出荷の資料作りをしないといけない、といった様々な業務が山積みになっている日々。
それでも、男性と同じ仕事をこなしても女性であるということだけで月給が1万円安く、1年間で12万円の給料の差があったそうです。

女性として働くことの難しさは、社内だけでなく社外でも。
新しい営業担当として高見さんが紹介されると、男性の店長から
「うちはもうランク落ちたんだ」
と言われた経験もあるそうで、“女性として働く”ことの厳しさを目の当たりにしたといいます。
仕事が部活の延長という考えや、スニーカーは“男らしいもの”という考えが業界全体にあったのか、スニーカー業界での女性の評価や見られ方は厳しかった当時。
女性だからという理由で心無い言葉を浴び、業界での疎外感を感じつつも、一部では性差・年齢・経験が理由にした差別もなく、平等に関係を築いてくれたお店もあり、そのお店とは今でも交流が続いているそう。
日本のスニーカー業界において欠かせない存在である高見さんも、「他に出来ることに何があるのかわからなかったので、やっていくしかなかった」と話し、さまざまな奮闘を駆け抜けた過去がありました。

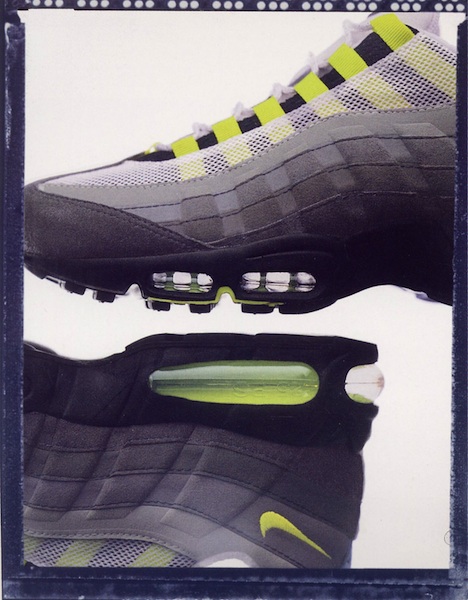 via FASHIONSNAP
via FASHIONSNAP